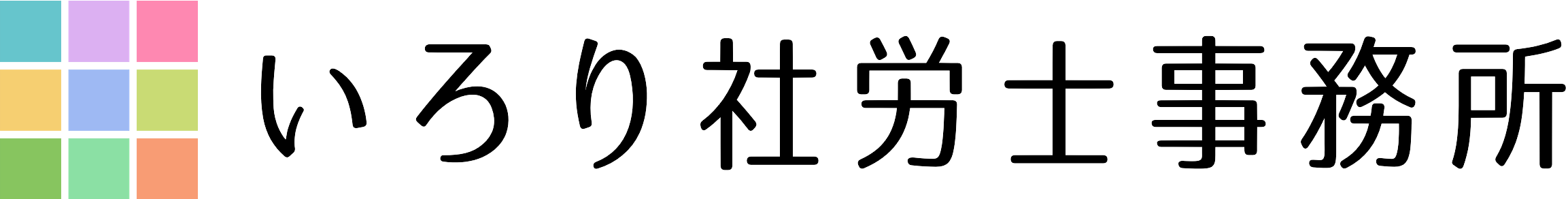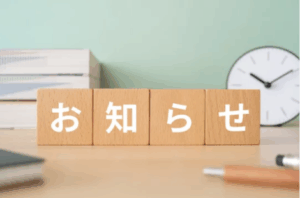中小企業に求められる具体的対応
2025年3月にフジテレビが公表した第三者委員会の調査報告書には、ハラスメントのリスクにどう向き合うべきかという点で、中小企業にも参考になる示唆が数多く含まれています。
ハラスメントの問題をを未然に防ぎ、また発生時に適切に対応するために、企業はどのような備えをしておくべきでしょうか。
ハラスメントに関する研修を実施する
ハラスメントを防止するためには、社内の意識を高める取り組みとして、弁護士や社会保険労務士などによる定期的な研修の実施が欠かせません。
従業員一人ひとりが、ハラスメントに該当する行為の定義やその境界線を正しく理解し、自分自身の言動を客観的に振り返る機会を持つことが重要です。
職場での何気ない一言や、業務上の指示、飲み会などの場面でも、受け手に不快な思いをさせていないかという視点を持つことが、未然防止につながります。
こうした研修は、単に法律やルールの説明にとどまらず、実際に起こりうる事例やロールプレイなどを通じて、自分ごととして捉えられるよう工夫することが効果的です。
特に、管理職や営業担当者など、部下や取引先と接する機会の多い立場の社員に対しては、より現場に即した実践的な対応力を養う研修が求められます。
たとえば、部下から相談を受けたときの初動対応のポイント、取引先との接触時に不適切な言動を目撃した場合の対応の仕方など、具体的なシナリオに沿った内容が望まれます。
また、単発の研修で終わらせるのではなく、定期的に内容を見直しながら継続的に実施することが大切です。
制度として整備することで、職場全体のハラスメントに対する感度が高まり、組織としての一体感や信頼性の向上にもつながっていきます。
ハラスメント防止指針を社外にも周知する
ハラスメントの防止に取り組むうえでは、社内の体制づくりだけでなく、取引先との関係性にも目を向けることが重要です。
従業員が安心して働ける環境を守るには、社外とのやり取りの中でハラスメントの芽を未然に摘む姿勢が欠かせません。
そのためには、自社がハラスメント防止に取り組む方針を明文化し、取引先に対してもその内容を丁寧に伝えることが求められます。
単なる形式的な通知にとどまらず、取引を継続するための共通認識として、ハラスメントのない環境づくりに協力を求める姿勢を明確にすることが重要です。
具体的には、業務委託契約書や発注書、基本契約などの文書に、ハラスメント防止に関する条項を盛り込む方法が有効です。
たとえば、取引先の従業員や役員が自社の社員に対して不適切な言動を行った場合の対応方針や、契約解除の可能性について明記しておくことで、一定の抑止力が働きます。
このような取り組みは、自社のリスクを回避するだけでなく、信頼できるパートナーと良好な関係を築くための基盤にもなります。
接待や会合への参加は完全に任意とする
接待や会合への参加は、特に一般社員については本人の意思を尊重し、任意とする運用が望まれます。
営業職など職務上の特性により参加が求められる場合もあるかもしれませんが、それでも可能な限り個々の事情に配慮した対応が求められます。
また、性別や容姿といった属性を理由に、特定の社員に同行を求めるようなことがないよう、社内のルールとして明確に定めておくことが重要です。
参加の可否はあくまで本人の意思によるものであり、強制的な雰囲気をつくらないよう、組織全体で意識を共有する必要があります。
外部通報制度の整備
ハラスメントの問題は、発生そのものを防ぐ取り組みと同じくらい、発生後の「気づき」と「対応」が重要です。
そのためには、従業員が不安や違和感を感じた際に、ためらうことなく声を上げられる通報制度の整備が欠かせません。
特に取引先からのハラスメントのように、社外の関係者が加害者となる場合には、社内での報告が難しくなりやすく、対応の遅れが事態を深刻化させる要因となります。
実際、フジテレビの第三者委員会報告書でも、被害が起きた時点で社内に相談が寄せられていたにもかかわらず、十分な調査や対策が取られなかったことが厳しく指摘されています。
被害者の声が「個人的な問題」として軽視され、組織としての対応が後手に回ったことが、長期的な人権侵害の放置につながったと報告書は結論づけています。
こうした教訓からも明らかなように、社内における問題発見の遅れは、結果として組織の責任をより重くし、社会的な信頼を大きく損なうことになります。
通報制度は、そうしたリスクを最小限に抑えるための仕組みであり、組織の健全性を守る重要なインフラといえるでしょう。
そのためには、社内に通報窓口を設置するだけでなく、匿名での相談や第三者機関による外部窓口も選択肢として用意することが効果的です。
外部の専門機関を活用することで、相談者が個人として特定される不安を軽減し、より安心して声を上げられる環境を整えることができます。
直属の上司が関係しているようなケースでも、外部窓口の存在は重要な役割を果たします。
また、こうした制度は用意するだけでなく、その存在を従業員にきちんと周知し、使いやすいものであることを理解してもらうことが不可欠です。
誰に、どのような方法で、どのような内容を相談できるのかを具体的に示したガイドラインや社内規程を整備しておくことで、制度の実効性が高まります。
たとえば、就業規則や社内ハンドブックにおいて、通報制度の利用方法、外部窓口の連絡先、匿名性の保証、不利益取扱いの禁止について明記することが考えられます。
加えて、通報内容の秘密保持や相談内容の扱い方に関する社内ルールを整えておくことで、通報者の安心感はさらに高まります。
通報制度は、組織が問題を可視化し、健全な職場環境を保つためのセーフティネットです。
表面化していない問題にいち早く気づき、組織として誠実に対応していくための仕組みとして、定期的な見直しと改善も必要です。
最後に
ハラスメントを未然に防ぎ、発生した際には迅速かつ適切に対応するためには、制度やルールだけでなく、組織全体の意識づくりが不可欠です。
今回取り上げたような研修の実施、社外への方針周知、接待慣行の見直し、そして通報体制の整備は、そのための具体的な第一歩です。
フジテレビの事例が示すように、見過ごされた小さな声や、形式だけの対応が、後に大きな問題へとつながる可能性があります。
だからこそ、日々の業務の中で従業員一人ひとりの尊厳を守ることを、企業全体の姿勢として明確に示していくことが求められています。
働く人が安心して声を上げられる職場は、結果として信頼される企業文化へとつながります。
少しずつでも確実に取り組むことで、組織の土台は確かに強くなっていくはずです。