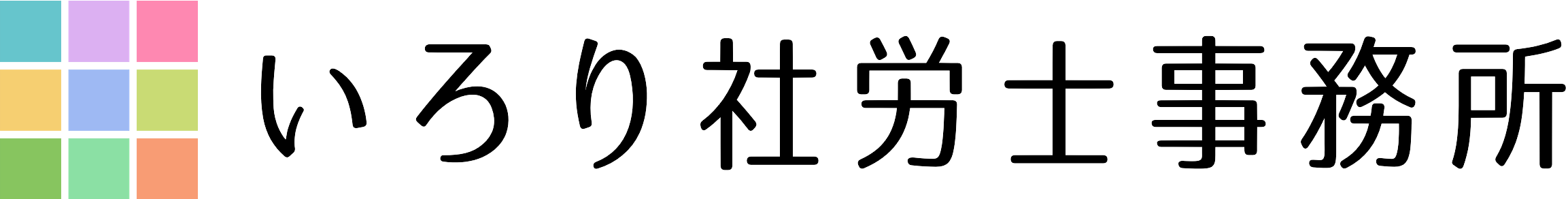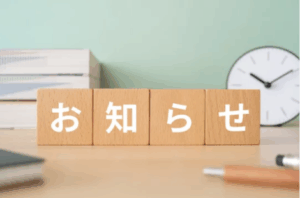第三者報告書が示唆するもの
2025年3月にフジテレビが公表した第三者委員会の調査報告書は、企業に突きつけられた現実をあらわにしました。
自社の社員が取引先のタレントから性的被害を受けたにもかかわらず、十分な対応が取られなかった結果、長年にわたって深刻な人権侵害が放置されたという内容です。
この問題は大企業に限ったことではなく、中小企業にとっても決して他人事ではありません。
多くの経営者は、ハラスメントや不適切な接待の問題について、どこか他人事のように考えてしまう傾向があります。
特に、社内ではなく取引先からの行為に関しては、「うちが直接の加害者ではない」という意識から、対応が後手に回ることも少なくありません。
近年では、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が浸透しつつあり、顧客や取引先による不当な言動が、企業にとって無視できない経営課題として捉えられるようになっています。
また、接待や会合の場で女性社員をいわば雰囲気づくりの役割として同席させる慣行は、今なお中小企業を中心に根強く残っています。
特に、運送業、製造業、建設業といった男性の比率が高い業種では、その傾向がより顕著に見られるのが現状です。
これらの問題は、いずれも企業の安全配慮義務違反という法律的な問題として捉えることができます。
このコラムでは、この報告書を起点に、取引先によるハラスメントへの対応、接待慣行の是非、そして企業がとるべき実務対応について詳しく解説します。
安全配慮義務とは何か
企業が従業員と締結する労働契約には、賃金支払いなどの基本的な約束のほかに、働く環境を安全・健康に保つ義務が含まれています。
これを安全配慮義務といいます。
法的には労働契約法第5条にその根拠があり、使用者は労働者の生命・身体・精神的安全に配慮しなければならないと定められています。
この義務は、工場や建設現場などでの物理的な安全対策に限られた話ではありません。
近年では、職場内の精神的な安全、すなわちパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントのない環境を整えることも含まれると考えられています。
そして、ハラスメントの加害者が取引先や顧客などの「社外の人」であったとしても、それが業務の一環で生じたものであるならば、会社には安全配慮義務が及ぶというのが通説的な理解です。
たとえば営業職の従業員が取引先との商談後の飲み会で不快な言動を受けた場合や、接待中に身体的な接触を受けた場合に、会社が何らの対応も行わなければ、労働契約上の義務違反となる可能性があります。
フジテレビの事例に見る安全配慮義務の欠如
第三者委員会の報告書では、まさにこの安全配慮義務の観点から、フジテレビの対応が不十分だったことが厳しく指摘されています。
報告書は、当時の被害リスクについて以下のように述べています。
「取引先との間で、あるいは取引先によって、性的暴力・ハラスメント等の人権侵害がなされるリスクが現実に存在していたにもかかわらず、CXとしてこのようなリスクへの調査や予防、発生後の対応が十分になされていなかったと認められる」(報告書 p.27)
ここで注目すべきは、「リスクが現実に存在していたにもかかわらず」と明示している点です。
つまり、取引先による不適切な言動が発生する可能性が想定できたにもかかわらず、会社側が調査や予防措置を怠ったことが問題視されているのです。
このような対応は、単なる管理不行き届きでは済まされず、結果的に従業員の人権を侵害する重大な事案へと発展しました。
従業員が被害を訴えた際にも、組織として迅速かつ適切な対応を取ることができなかったことが、さらに問題を深刻化させたと報告書は結論づけています。
接待慣行とジェンダー意識の問題
報告書では、接待や会合の際に、性別や容姿によって女性社員が選ばれ、同席させられるという慣行が存在していたことも明らかにされました。
「容姿・年齢・性別に着目して、若手女性社員を会合等に招集する慣行が一定程度存在していたと認められる」(報告書 p.22)
このような接待のあり方は、現代の価値観から見れば明らかに不適切です。
女性社員を「場を華やかにする存在」として扱うことは、性差別的な固定観念に基づいたものであり、企業文化の改善が求められるポイントです。
接待そのものを否定するものではありませんが、そのあり方にジェンダーによる役割分担や暗黙の期待が含まれていれば、それは時代にそぐわない慣行となります。
仮に本人の意思で参加していたとしても、それが自由意思に基づくものかどうか、無言の圧力が働いていなかったかを慎重に見極める必要があります。
ハラスメント対策
中小企業が取り組むべき具体的なハラスメント対策については、以下の関連記事をご覧ください。
最後に
今回の報告書は、大企業における不祥事として扱われがちですが、企業の規模に関係なく、根本の問題はどの会社にも共通しています。
従業員が安心して働ける環境を整えること、それが経営者のもっとも重要な責任の一つであることを、改めて認識する機会としたいところです。
安全配慮義務は、単なる道徳ではなく、明確な法的責任です。
この義務を軽んじることは、従業員の健康や尊厳を損なうだけでなく、会社の信用や法的リスクにも直結します。
経営者自身がこの義務の重さを理解し、企業文化の見直しと制度整備に主体的に取り組むことが、組織の持続的な発展を支える礎となります。